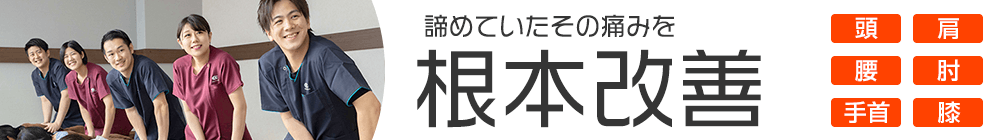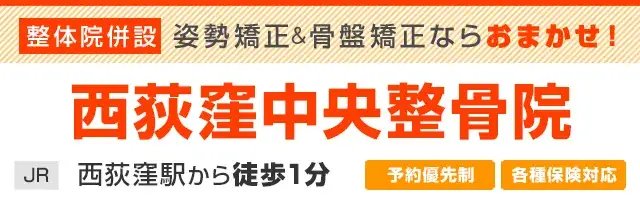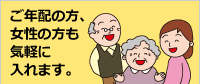オスグッド
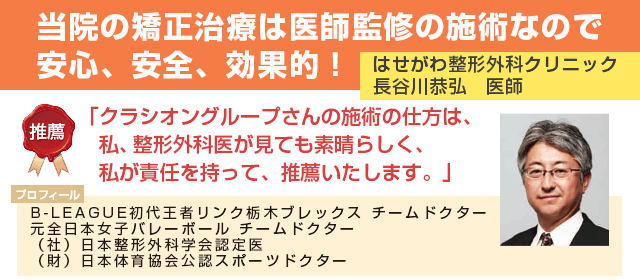

こんなお悩みはありませんか?

膝下に突起が現れ、目に見えて膝の形が変化してきた
膝に痛みや腫れが生じる
膝が熱を帯びることで、だるさや不快感を感じやすくなる
正座がしにくくなる、またはできなくなる
膝の動きが悪くなり、運動に支障が出ることがある
ジャンプやしゃがむ動作に困難を感じる
日常生活でも膝の違和感に悩まされる場面が増えてきた
オスグッドについて知っておくべきこと

成長痛とオスグット病の違い
成長痛とオスグット病には根本的な違いがあります。成長痛は、骨が成長する部位である骨端軟骨が短期間で成長する際に、筋肉や腱が引っ張られ、痛みが出るものです。また、痛みの部位が特定されておらず、痛みを感じる時間帯は夕方から夜にかけて現れることが特徴です。
一方で、オスグット病は筋肉が骨を引っ張る際に痛みが生じるもので、根本的に異なります。痛みが出た際に類似する成長期のスポーツ障害として、膝離断性骨軟骨炎があります。膝の痛みのほかに、関節内で軟骨が剥がれることにより、関節の不安定感や引っ掛かり感を訴えることもあります。
症状の現れ方は?

オスグット病は、サッカーやバスケットボール、バレーボールなどを行っている成長期の子どもに多く見られるスポーツ障害です。ボールを蹴る際のシュートやキック動作、走っている際のストップ&ダッシュ動作、ジャンプなどに代表される、大腿四頭筋の伸縮や酷使、同じ動作の繰り返しによって症状が現れることが特徴です。
成長期には、骨の伸びる速度が早く、筋肉の柔軟性が骨の成長スピードについていけなくなるため、筋肉が付着する部位に引っ張られるストレスがかかりやすくなります。これにより、膝のお皿の靭帯が付着する脛骨粗面という部分が剥がれ、オスグット病が発症します。
その他の原因は?

オスグット病は成長期に起こることが主ですが、大人になってから再発することもあります。その原因として、大腿四頭筋の柔軟性低下、膝の使いすぎ、足首や股関節の可動域が狭いことが挙げられます。
大腿四頭筋の柔軟性が低下すると、屈伸運動をするたびに脛骨粗面が強く引っ張られ、オスグット病を発症しやすくなります。姿勢が悪いと四頭筋の柔軟性が低下することがあるため、体の重心が後方に偏っていないかも注意が必要です。
また、足首や股関節の可動域が狭いと、膝にかかる力が分散されず、オスグット病が再発する原因となります。
オスグッドを放置するとどうなる?

骨の成長には、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル、炭水化物やたんぱく質などの栄養素が重要です。また、運動をすることによって血液循環が促進され、骨や軟骨に栄養が行き渡りやすくなります。さらに、骨の成長を促進する要素として成長ホルモンも重要です。
成長ホルモンは1日中分泌されるわけではなく、主に就寝中や運動後に多く分泌されます。オスグッド病を起こすと、痛みにより十分な運動ができなくなることがあります。これにより、成長ホルモンの分泌が十分でない状況が続き、骨の成長が悪化する可能性があります。
痛みを放置していると、このような問題が起こる可能性がありますので、早期の対処が大切です。
当院の施術方法について

オスグッドで痛む場所は主に膝下です。これは、太ももの筋肉である大腿直筋が固まり、膝下にある脛骨粗面の付着部を引っ張ることによって痛みが生じるためです。
大腿直筋が硬いからといって、単にそれを緩めれば痛みが軽減されると思われがちですが、逆効果になることがあります。下手にマッサージを行うと、筋肉が反発してさらに硬くなり、痛みが増すことがあるため注意が必要です。
そのため、筋膜ストレッチを施術に取り入れ、殿筋、ハムストリング、ふくらはぎ、股関節などの硬さを取り除くことで、大腿直筋の抵抗を抑えます。その後、指圧などで大腿直筋を緩めていきます。
改善していく上でのポイント

オスグッドになってしまった際に、一番やってはいけないことは痛みを我慢することです。痛みを我慢して運動を続けると、症状が悪化し、ひどい場合には手術が必要になることもあります。
オスグッド病の基本的な施術は、患部を休めることです。患部以外の部分はトレーニングを続けることが可能ですが、痛みを我慢して運動を続けると、症状が悪化し、最終的には手術が必要になることがあります。
オスグッド病は通常、特別な施術を行わなくても症状が軽減することが多いです。ただし、膝を使う動き、ジャンプ、走るなど、症状を悪化させる動きを繰り返すと、長引く可能性があるため、動き方に制限を加え、無理なく行うことが重要です。
監修

西荻窪中央整骨院 院長
資格:鍼師、灸師
出身地:埼玉県行田市
趣味・特技:映画鑑賞、1人飲み